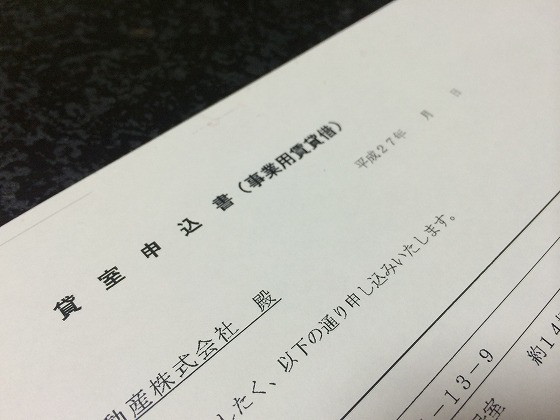2015年2月13日の金曜日の時点において、僕は自分の他に当物件にどれほどの応募があるのか、そして、どんな応募があるのか、全く知らされていなかった。不動産会社にとって“誰と契約するか”の判断材料は「資金力」と「与信」の他になく、僕にはそのどちらもない。もし不動産会社が提示した家賃をそのまま飲む応募者がいれば、レースは終了。仮に、僕と同じような立場の人間からの応募しかなければ、熾烈なデッドヒートとなる。つまり、それは家賃及び造作譲渡金をどれだけ多く払えるかをめぐるレースで、誰かが引き下がらないかぎり、金額はオークションのようにどこまでも吊り上っていく。
したがって、申込みの段階で自分が払える家賃をいくらにするかは極めて重要なポイントとなる。不動産会社が提示した金額で申し込むことは資金的にできない。それよりも低い金額で申し込むことになるが、提示金額をあまりに下回るのもリスキー。「なめてるのか?」、「話にならない」と思われてしまうかもしれない。
結局、自分が現実的にシミュレーションして、現実的に支払えるであろう金額からほんの少し上乗せした額を自らの提示額とした。そしてその上で、仮に金額が吊り上っていった場合、ここまでなら出せるという上限金額もあらかじめボーダーラインとして設けた。もしそのボーダーを超えていくのであれば、その時は潔く諦め、潔く切り替える。「契約」がゴールではないのだ。
さらに言えば、こうしたレースにおける脅威は不動産会社の匙加減次第になりかねないということ。各応募者がどれだけの金額を提示しているかは不動産会社から口頭で伝えられるのみで、その真偽を確かめることはできない。つまり、架空の応募者を立てて、架空の金額を伝えてしまえば、応募者はその出鱈目なフィクションと戦うことになる。例えば「他の応募者は○○万円出すって言ってるんですよ」と言われてしまえば、その時点で風下にまわることは避けられず、そうした悪意(と言っていいだろう、この場合)の前に、僕のような立場の人間は極めて非力と言える。けれど、それは当然に想定しておかなければならないリスクであり、だからこそ、流されないように毅然としてレースに臨まなければならない。重複するが、僕には潤沢な資金も与信も、キャリアも経営の知識もない。限りなく一般的な一般人であり、むしろ、フリーターや世界一周の経験を考慮すればそれ以下にあたるだろう、一般的には。
熱意や意欲などそうした類のものはこのレースにおいて、何物にもならないと自覚しながらも、今の自分にできることをやり抜くしかない。そして、それは初めて池尻さんに出会った時に提出したペラペラな店舗計画書を練り直し、洗練させ、改めて池尻さんに共有、確認してもらうことだった。競争を出し抜くための有効かつ効果的な手立てだとは到底思えなかったが、それぐらいしかできることがない。
そして迎えた2月13日。33歳の誕生日。世の中、そう甘くはないし、そううまくはいかない。アンハッピーバースデイになる覚悟はできていた。
「山本さんで行きますんでよろしくお願いします」
と、池尻さんは席に着くなり言った。渾身の計画書はまだバッグの中に眠ったまま。ストローも封を切ってない。
「え…?」
「もう、上にも通して、許可もらってるんで」
「あの他の応募者の方は…?」
「何件か内見ありましたけど、皆さん、中途半端なんですよね。やるのか、やらないのかはっきりしないし、やりたいのか、やりたくないのかもよくわからない。そのくせ、問い合わせはけっこう来て、電話は鳴りっぱなしです。私がこう言うのもなんなんですが、それがけっこう煩わしいんです。電話対応ばかりで他の仕事が進まないんですよね。私としては、他の応募者を募らなくても、やる気のある有望な方がいるのであればその方に任せて早く切り上げたいと言うか…」
「あ、あの店舗計画書を練り直してきたのですが…」
「拝見します」と言って、池尻さんは更新した計画書を手に取った。そして、僕が設定した家賃が表記されているページに目をやった。
「御社の提示金額が○○万円なのに対し、僕の設定が○○万円というのは安すぎるとも思うのですが、あの立地を考えるとこれくらいが現実的なラインになるかと思っています。いかがでしょうか…?」
そう、おそるおそる言うと、特に試算する素振りも見せず、「この金額で問題ありません。上には私の方から説得しておきます」と言って、あっさりと了承された。
「では早速」と言って、池尻さんは賃室申込書を取り出した。
「もし、問題なければこちらに御記入お願い致します」
勿論、こちらに問題はない。と言うより、問題がないのが問題だった。
あまりの肩透かしに、肩に力が入らないまま、僕は申込書の記入箇所を順々に書き進めた。僕は誰もいないサーキットの中で、一人でデッドヒートを繰り広げていたのだ。
家賃を記入し終えると、
「本当にその金額でいいんですか?」
と池尻さんは言った。見たことのない、意味深で、神妙な顔つきを池尻さんはしていた。